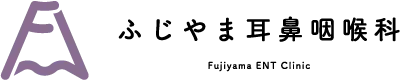診療案内
みみ 耳
こんな症状ありませんか?
聞こえにくい・難聴/めまい/痛み/かゆみ/違和感/耳だれ/耳あか/耳鳴り/耳閉感/耳のひびき/はれ など
疾患
耳あか・外耳道炎/難聴(補聴器) /中耳炎/めまい/耳鳴り/耳管機能障害
-
耳垢(みみあか)の除去のみでも受診可能です。
綿棒や耳かきなどで頻回に耳掃除をすることで外耳道を傷つけることや、逆に耳垢がたまりやすくなったりもします。外耳道を傷つける(外耳道炎)と耳のかゆみや痛みを生じますので外耳道が傷ついている場合は耳垢の適切な除去と外耳道の適切な処置を行って治療を行います。 -
左右どちらかの耳の聞こえが急に悪くなったり、急に耳鳴りが強くなったりします。きっかけが全くない場合や急に大きな音を聞いたときに発症したりします。
急な難聴はできるだけ早く治療を開始する必要があり (一週間以内)、高度難聴が認められる場合は、入院加療の適応がある場合もありますので、基幹病院に紹介となる場合もあります。そのため早期の検査が必要です。 -
聴力検査や他の検査を行い、すぐに治療が必要な難聴であるか判断し、難聴の予防について説明を行います。
-
軽度難聴から高度難聴に適応になります。
難聴の精査を行い、治療が必要な病気に関しては治療を行ったあとに補聴器装用をすすめます。
日本人の補聴器装用は、他の先進国と比べ装用率が低いと言われています。高齢者の方には軽度難聴でも装用することによってメリットがあると言われおり、認知症の予防にも有効と言われています。軽度難聴でも補聴器装用をすすめていますのでお気軽にご相談ください。POINTことばのききとりは、耳に音が伝わり頭の大脳で理解することで成り立っています。徐々に大脳での聞き取り能力が衰えることにより、音は聞こえるけれども言葉として聞こえなくなっていきます。補聴器装用下でもまわりの方に協力してもらい、ゆっくり話してもらうことで言葉として理解も可能となります。
-
飛行機に乗った後に起こる航空性中耳炎、難聴をきたし痛みが強いムコイド型中耳炎、耳管機能が悪くなり発症することが多い滲出性中耳炎、喘息との合併が多い好酸球性中耳炎、膠原病の一つの血管炎で発症する中耳炎など特殊な中耳炎があります。聴力検査や各種薬剤との反応を見たりすることにより鑑別できます。
-
中耳炎のフォロー、術後フォローは行っておりますのでご相談ください。
-
耳の中に前庭、三半規管と呼ばれるバランスを司る器官があり、それが原因でめまいを起こすことがあります。一番多いめまいは、良性発作性頭位めまい症とよばれる三半規管にある耳石が迷入して起こるめまいです。頭を動かしたときに1分程度ぐるぐる回り、また頭を動かせばめまいがぐるぐる起こります。めまいはひどいですが、適切に対処すれば9割近くは2週間以内に治ります。
-
名前は有名ですがめまいの約10%と比較的めまい疾患では少ない病気です。繰り返すめまい、変動する聴力などの特徴的な症状を伴います。一回だけの診察だけでは確定診断することは難しく、長期的な経過を見ることが診断の鍵となります。
-
回転性めまいが数日続いて、発症当日は歩行が困難になることがあります。強い吐き気を伴い、数日間の安静になることが多いです。発症診断後は早期のリハビリが重要となります。
-
一過性脳虚血障害/高血圧性めまい/片頭痛性前庭障害/加齢性前庭障害/前庭性発作症/頸性めまい/PPPD/小脳梗塞/心因性めまい
-
高音の音が聞こえづらくなると耳鳴りが症状として出てくることがあり、ジーやキーンなどの音が静かになるところでは気になるようになります。
まずは聴力検査を行い、難聴がないか調べます。片側性の難聴があれば、その他の検査が必要となる場合があり、両側とも耳鳴りがある場合などは、内服加療の適応となります。一般的なビタミン剤や血流改善薬、耳の血流を改善する炭酸ガス吸入などを試して改善するか経過を見ます。難治性のこともありますので発症初期段階での受診を勧めます。 -
耳と鼻とをつなぐ耳管。耳管は耳の圧を調節しており、通常は閉じていますが、つばを飲み込んだり、嚥下すると自然と開いて圧を調節しています。わかりやすいのは、飛行機に乗ったときや高いところに上ったときや新幹線でトンネルを通るときなどです。
その耳管が開き気味になると耳管開放症、つまり気味になると耳管狭窄症です。耳管開放症は、耳閉感、響く感じが継続し、耳管閉塞症も耳閉感や難聴です。耳管閉塞症は滲出性中耳炎に移行する場合があります。
はな 鼻
こんな症状ありませんか?
鼻みず/鼻づまり/くしゃみ/はな・ほおの痛み/嗅覚障害/鼻血/後鼻漏/変なにおいがする など
疾患
アレルギー性鼻炎/副鼻腔炎/好酸球性副鼻腔炎 /高齢者の鼻炎・鼻水 /嗅覚障害
-
くしゃみ・鼻みず・目のかゆみなどの症状が主体となります。ハウスダストやダニなど一年中症状が出る方もいれば、スギ、ヒノキ、ブタクサなどの季節性の場合もあります。まずは抗アレルギー剤などの内服、点鼻、鼻洗浄などが有効です。難治性の場合は、局所的な粘膜焼灼やスギ、ダニの舌下免疫療法などがあります。
POINTアレルゲン舌下免疫療法(スギ・ダニ)
10年ほど前から本格的に始まった治療で少量の抗原(アレルギー物質)を毎日内服することによって症状を軽減する治療です。少なくとも3年ほどの内服加療が必要です。開始直後でも効果を実感できる場合もあります。通常の内服加療で症状の軽減が少ない人やアレルギーを治したい人に勧めています。
治療の開始時期が決まっていますので、希望の方はご相談ください。POINT抗IgE抗体 生物学的製剤
花粉症に対してシーズン中に2-4週おきに注射行い、症状軽減を目指す治療です。他の加療方法に比べ、症状軽減が強く期待できます。
検査にてクラス3以上のアレルギーがあることが必要ですのでお気軽にご相談ください。 -
副鼻腔という空洞が頬や目の間、おでこの下にあり鼻につながっています。副鼻腔に膿などの貯留液がたまり炎症を起こした状態です。症状は急性の時は顔面の痛み、膿性の鼻水、慢性の場合には鼻閉、鼻水、嗅覚障害などです。原因はかぜが一番多いですが、かぜが治った後も炎症が続く場合もあります。また、アレルギー性鼻炎や好酸球などでポリープが鼻の中にできて、副鼻腔の入り口をふさぐことで発症する場合もあります。
その他の原因として、歯が原因である歯性副鼻腔炎、かびが原因である真菌性副鼻腔炎、腫瘍性のものがあります。
歯性副鼻腔炎は上の奥歯が原因で副鼻腔炎を発症する為、歯の治療が有効な場合もあります。
真菌性副鼻腔炎はカビが副鼻腔に寄生し、糖尿病やリウマチの治療をされている方に比較的多く認められます。基本的には手術的な加療となります。
原因に沿った、内服や点鼻、鼻洗、精査や手術などの治療が必要になります -
通常、蓄膿症とよばれていた病気とはちょっと異なる病態で手術してもすぐに再発、ポリープが出来てしまうような状態になります。通常の蓄膿症は、細菌や白血球の好中球が原因でしたが、好酸球性副鼻腔炎は白血球の好酸球が過剰に反応を起こしてポリープなど出来てしまう病態で、症状はどちらかというと鼻汁よりは鼻閉や嗅覚障害が症状として出ることが多いです。
通常の蓄膿症と異なり、抗生剤の効果は限定的になります。点鼻、噴霧ステロイド剤や抗ヒスタミン薬などの抗アレルギー剤などが使用されることが多いです。 -
加齢の影響で鼻腔の構造、鼻粘膜の組織的変化が生じます。
構造的な変化は入口部の軟骨が弱くなり入口部が狭くなったり、粘膜表層は線毛の減少し、血流が減少します。また、年齢とともに粘膜の昜刺激性のため、刺激に対して過敏に反応して鼻汁分泌をきたします。すなわち、普段は乾燥気味であるが何らかの刺激に対して反応し鼻水が止まらなくなるという制御が難しい鼻症状を呈することがあります。
できるだけ粘膜を乾燥しないようにすることや交感神経を休ませることによって症状が軽くなる場合があります。 -
頻度が高いのは、かぜの後(コロナも含む)の嗅覚障害や副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎による嗅覚低下です。かぜの後に長引く嗅覚消失は改善が悪い場合がありますので早めの受診をおすすめします。
副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎による嗅覚障害は、副鼻腔炎や鼻炎の治療を行い、改善なければ手術なども適応になります。
高齢の方の嗅覚低下は、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患と嗅覚低下との関係が最近注目されています。
のど/くち/こえ/飲み込み(嚥下)
こんな症状ありませんか?
のどの痛み/違和感/つまり感/咳・痰/声がかすれる/声が出しにくい/息苦しい/味覚障害/口内炎/嚥下・飲み込みの異常/のど・口に何か流れてくる
疾患
咽頭痛・咽頭炎 /口内炎 /味覚障害 /アデノイド・扁桃肥大/声がれ(嗄声) /咳/嚥下障害
-
鼻の奥には上咽頭、一番腫れやすい扁桃腺(中咽頭)の炎症です。 咽頭や扁桃腺は急性の細菌感染やウイルス感染のが多く、上咽頭は慢性的に炎症を起こす場合があります。
ウイルス性咽頭炎についてウイルスの咽頭炎に呈しての治療は、治す薬は無いと言われています。抗生剤は細菌感染に対して効果があり、ウイルス感染には効果はありません。うがいや吸入、トローチや抗炎症剤、安静、栄養補給などで治していきます。
-
溶連菌などの細菌感染で起きる炎症が扁桃周囲で起こります。のどのいたみ、発熱、つまり感が生じます。
咽頭痛の程度、咽頭の腫脹の具合で重症度を判定し、抗生剤治療が主体となります。
内服抗生剤が効果無い場合は、強い抗生剤や点滴の抗生剤が必要な場合もあります。
重症化すると扁桃腺周囲に膿がたまることがあり、そこまでなると点滴加療、手術などが必要となります。 -
のどの違和感については上咽頭炎、逆流性食道炎、喉頭アレルギー、慢性咽頭炎、副鼻腔炎、乾燥・脱水、鼻炎など原因は多岐にわたり、なかなか症状が取れない場合があります。炎症がないかどうか、できものがないかどうか、鼻に異常がないかどうか、など検査していきます。
-
粘膜の欠損病変の深さにより、浅い病変からアフタ→びらん→潰瘍と分けられます。
原因はいろいろあり、アフタ性口内炎、ヘルペス性口内炎、ヘルパンギーナ、クローン病ベーチェット病、天疱瘡など多数に上ります。
多いのはアフタ性、ヘルペス性などです。アフタ性の場合は軟膏などの塗布、ヘルペス性の場合は抗ウイルス薬の内服が有効です。難治性の場合は、免疫系の検査が必要な場合もあります。 -
味の司る細胞である味蕾は舌全面や口腔内の軟口蓋粘膜や扁桃腺周囲にも存在します。味蕾は唾液に溶けた味物質を介して神経に伝達され、脳の中枢に伝わります。その味蕾は亜鉛低下により機能低下しやすいと言われており、亜鉛欠乏の加療をすることにより改善することが多いです。その他の病気もありますので発症して早めの相談をおすすめします。
-
アデノイド(鼻の奥の扁桃)は一般的に就学前後に生理的肥大のピーク、また、扁桃腺(口蓋扁桃)おおむね10歳頃が一番肥大するといわれ、それ以降は退縮が進み、思春期以降に肥大は消失すると言われています。ただ、大きいままの症例も見られますので睡眠障害などが見られる症例については切除の対象となります。
一過性に肥大する場合は炎症によって腫大しますので、細菌感染の場合は抗生剤による加療、ウイルス感染の場合は痛み止めなどの対症療法になります。 -
かぜになると声ががらがら声になることがありますが、それが継続すると検査が必要となります。声を出す器官である声帯の問題をファイバーで観察します。声帯の動きやポリープや一過性の炎症や腫瘍などの鑑別が必要になります一過性の炎症や小さめのポリープなどはネブライザー(吸入)加療や内服が有効な場合があります。発症当初に集中的に行うと改善します。大きめのポリープなどは手術が必要な場合には専門医がいる医療機関に紹介いたします。
また、声帯の動きが悪くなっている場合には甲状腺や縦隔、肺の腫瘍性病変を否定する必要があります。 -
呼吸器疾患以外にのどや鼻が原因になる場合があります。副鼻腔炎や鼻炎で口や咽頭に鼻みずが流れ込み、咳を誘発する場合があります。副鼻腔炎や鼻炎の加療することで改善することもあります。
-
高齢化に従い、嚥下の機能も低下していきます。具体的には粘膜の知覚の低下、反射の低下、筋力の低下をおこして飲み込みの機能も低下していきます。それに対応した、食べ方が必要になってきます。
ファイバーによる嚥下機能を観察して評価します。
嚥下機能を維持するために、その人にあった姿勢や食事形態をアドバイスし、誤嚥性肺炎予防には、うがいや歯磨き、入れ歯の洗浄など口腔環境の衛生が必要です。
フレイルの予防も重要になってきます。フレイルとはフレイルとは、高齢者において身体的、精神的、社会的な機能が徐々に低下し、脆弱な状態になることを指します。具体的には、筋力の低下、体重の減少、歩行速度の低下、疲労感、身体活動の減少などが見られます。これらの要因が重なり合うことで、日常生活における自立が難しくなり、介護が必要となるリスクが高まります。
くび(頭頸部)
こんな症状ありませんか?
首にしこりがある/首が腫れた/耳の下が腫れた/あごの下が腫れた/リンパ節が腫れた/赤くなっている
主に耳鼻咽喉科で扱うのは、くびの前、両側横、あごの部分の腫れ、痛み、しこりなどです。
痛みを伴う腫れは早めの受診をおすすめします。中には早急に治療を開始し無ければならない炎症性のものもあります。
疾患
耳下腺の腫れ(耳のまわりの腫れ)/甲状腺の腫れ/あごの下の腫れ(顎下)/リンパ節の腫れ /その他
-
耳の前から下、後ろにかけて唾液を出す耳下腺という器官があり、口腔内と交通しており唾液を分泌しています。一過性に感染を起こす場合があります。反復することもあり(反復性耳下腺炎)、細菌感染起こすと抗生剤の加療を行う必要もあります。
そのほかに、おたふくかぜや唾石、腫瘍などの原因もあります。腫瘍性のものに炎症を起こす場合もあります。まずは炎症の治療を行い、炎症が落ち着いて腫瘍性を疑う場合は画像的な検査などが必要になります。 -
かぜやウイルスの影響で急性に腫れ、痛みが伴う場合があります。必要に応じて、内服加療を行います。また、腫瘍性の場合には、エコーやCTの検査が必要となります。
亜急性甲状腺炎/甲状腺腫瘍/下咽頭梨状窩瘻/バセドウ病/橋本病 など -
あごの下には、口腔内と近い部分で顎下腺という唾液を出す唾液腺があります。あごの下の腫れは、大部分は口腔内の炎症、歯の炎症、顎下腺の炎症や腫瘍が大部分を占めます。早急に治療を開始しなければならない炎症性の病気もありますので、早期の受診を進めます。
-
くびのリンパ節腫脹は、かぜ、血液疾患、特殊感染症、がんや他の病気の原因など多岐にわたります。徐々に大きくなる場合、数カ月間も腫れている場合は、精密検査が必要となります。
かぜの場合などに腫れることが多いですが、そのような場合は数週間ほどで腫れは改善します。
その他
こんな症状ありませんか?
かぜ/いびき・無呼吸/顔面神経麻痺/顔が腫れた/口が開きにくい/癌が心配
疾患
かぜ /いびき・無呼吸 /顔面神経麻痺
-
風邪症状は、副鼻腔炎、扁桃炎、喉頭炎など耳鼻咽喉科で診られる病気も多く認められます。
-
睡眠障害医療は耳鼻咽喉科、精神科、呼吸器内科、循環器内科など様々な診療科が実施しています。
いびきや無呼吸によって睡眠障害がおき、日中の眠気、集中力低下など生じます。無呼吸の症状によって、心臓や精神や身体に様々な影響が出てきます。
耳鼻咽喉科では口峡の広さ、鼻副鼻腔や舌根部の状態などをファイバーで観察し、評価します。また、当院では簡易検査を実施することができ、必要があれば、精密な無呼吸の検査を他の医療機関に依頼します。POINT乳幼児~小児のいびき・無呼吸
小児の原因は、かぜ、アレルギー性鼻炎、アデノイド肥大、扁桃肥大がほとんどの原因を占めています。一過性の場合は投薬治療、持続的な症状には手術的な療法を行っている場合もあります。当院ではまず投薬治療を行い、改善無ければ手術可能な病院への紹介行いアデノイド扁桃腺の切除をすすめています。
POINT小児以降~成人のいびき・無呼吸
年齢が上がるにつれて、アデノイド肥大や扁桃肥大の原因は少なくなっていきます。舌根沈下や最近は顎が小さくなってきておりそれによる舌根沈下を認める場合が多いです。治療として、睡眠指導やマウスピース、CPAPなどがあげられます。
-
手足の麻痺やその他の麻痺を起こさずに片側の顔の動きだけが悪くなることがあります。
口から水が漏れる、眼が完全に閉じないなどで気がついたりすることがあります。また、耳が痛くなったり、耳のうしろが痛くなったりします。
末梢性の顔面神経麻痺では早期の治療開始が重要になります。
高度麻痺の場合は、入院加療をおすすめしていますので耳鼻咽喉科医総合病院に紹介いたします。
ヘルペスウイルスが関与しているのではないかと言われており、抗ウイルス薬と神経の腫れを減らすステロイドという薬を使用することが多いです。 -
1顔面神経麻痺、2耳のまわりの水疱形成、3難聴(めまい)、の症状が同時期に現れる帯状疱疹ウイルスが原因で起こる病気です。
症状が3つ出ない不完全型も多く認めます。改善率が通常の末梢顔面神経麻痺に比べ悪いために顔面神経麻痺が重度の場合には入院で点滴加療を行う場合があります。
発症早期に治療開始が望ましいと言われています。早めの受診を勧めます。
こども 子供
こんな症状ありませんか?
耳が痛い/聞こえが悪そう/鼻水が多い/いびき・無呼吸/かぜ症状/鼻が痛い/首が腫れた など
お子様は症状がわかりにくいことがありますので気になることがありましたらご相談ください。鼻炎、中耳炎などを主に診療させていただきます。
疾患
鼻炎・かぜ /中耳炎/いびき無呼吸
-
アレルギー性やウイルス感染での原因が多く、子供の上気道炎の多くはウイルス感染が原因です。治療には症状緩和のための抗アレルギー剤、去痰剤や解熱剤や適切な休養が重要です。必要に応じて抗生剤の投与も検討します。
感染では家庭内や学校、幼稚園などの集団生活での感染予防が重要となってきます。POINT定期的な手洗い・マスクの着用・うがいの励行・休息と栄養
耳鼻咽喉科では吸入や鼻汁吸引などをこまめに行うことができます。
-
上気道炎(かぜ)の時やその後になることがあります。
上気道炎の時になる中耳炎は痛みや発熱を伴うことがありますので比較的わかりやすいです。かぜの後になる中耳炎は、自然と治ることが多いですが治らない場合もあります。
滲出性中耳炎と呼ばれ、痛くない中耳炎とも言われています。痛くないので、子供が訴えられないことが多く、知らず知らずのうちに難聴などの症状、耳の発達の障害になることがあります。聞き返しが多い、呼んでも返事しなくなった、耳の聞こえが悪そうだなどの気になることがありましたら、一度耳鼻咽喉科受診をおすすめします。 -
小児の原因は、かぜ、アレルギー性鼻炎、アデノイド肥大、扁桃肥大がほとんどの原因を占めています。かぜやアレルギー性鼻炎などの一過性の場合は投薬治療を行い経過観察します。投薬治療でも改善見られない場合、アデノイド・扁桃肥大が著明な場合は手術的な切除療法も選択肢としてあげられます。